地球環境の負荷軽減
人々の暮らしや経済を含め、すべての生命活動は地球の豊かな恵みに支えられています。資生堂は創業以来、大地の恵みへの畏敬と感謝を、事業の根幹と位置付けてきました。近年では、気候変動や生物多様性の損失、プラスチック汚染など、経済活動が自然環境に与える影響が地球規模で無視しえないほど大きくなり続けています。資生堂グループが、100年先も輝きつづけ、世界中の多様な人々から信頼される企業になるためには、地球環境の持続可能性と事業成長とを両立させていくことが、極めて重要と認識しています。資生堂は、事業に伴う環境負荷の低減に向けてバリューチェーン視点で課題を抽出し、長期の目標を設定して、全社をあげて取り組みを進めています。
「CO₂」においては、自社サイトからの排出だけでなく、バリューチェーンからの間接排出についても削減の対象として気候変動の緩和と適応に努めるとともに、気候変動に関連する事業リスクの最小化と、機会の最大化に努めます。「水資源」では、自社サイトにおける水消費量の削減とともに、ステークホルダーと連携しながら流域視点での持続可能な利用を推進しています。「廃棄物」では、サーキュラーエコノミーの考え方に基づく、資源の最適な利用を図っています。
環境方針はこちら
CO₂排出量の削減
気候変動は、気象災害や水不足、生物多様性の損失といった環境問題に加えて、健康被害や国土の喪失など多くの社会問題をも引き起こしています。このため世界では、産業革命以前と比べた平均気温の上昇幅を1.5℃未満に抑えることが国際目標として合意され、世界各国・各地域でネットゼロに向けた努力が続けられています。2024年には、気温上昇が過去最高を更新して上昇幅が1.55℃を記録し、国や地域レベルの対策だけでなく、企業の活動においてもさらなるCO₂※1排出削減の努力が求められています。
資生堂は「パリ協定」と「グラスゴー気候合意」に賛同し、気候変動対応を重要課題として捉えています。2050年のネットゼロを長期目標として、またそのための中間目標として2030年に向けて1.5℃目標に則した科学的根拠に基づくCO₂排出量削減目標(Science Based Targets)※2を設定し、SBTiから認証を受けています。再生可能エネルギーへの切り替えや、エネルギー使用量削減・エネルギー効率の向上などの取り組みに加えて、Scope 3と呼ばれるバリューチェーンからの間接的な排出についても、ステークホルダーとの協働を通じてCO₂排出量の削減を推進しています。

- ※1:CO₂:通常、温室効果ガスはCO₂、CH₄、N₂O、HFCs、PFCs、SF₆、NF₃を指しますが、本レポートでは特に断りのない限り、これらの温室効果ガスをCO₂と表記しています
- ※2:Scope 1、Scope 2、およびScope 3。SBT(Science Based Targets)イニシアティブ(SBTi)より認定を取得
エネルギー消費由来のCO₂排出(Scope1・Scope2)
企業活動におけるCO₂排出量削減のためには、バリューチェーン全体での取り組みが必要です。その基盤となる活動として、資生堂は自社サイトで使用される電力や燃料からのCO₂排出量削減を着実に進めています。
再生可能エネルギーの利用
資生堂では、グローバルの全工場・オフィス・研究拠点で再生可能エネルギーの利用を進めています。全社の電力における再生可能エネルギー比率は、2024年度には89%となりました。全11工場・自社物流センター、資生堂ジャパンの全自社ビルで、すでに100%再生可能エネルギー切り替えを完了しています。各国各地域の10工場※では太陽光パネルを設置しているほか、中国地域においては2023年に全拠点で100%切り替えを完了しました。さらに、中国・資生堂麗源化粧品有限公司(SLC)の工場を含む北京事業所ではカーボンニュートラル認証コード(PAS2060-2014)の要件を満たし、カーボンニュートラル認証を取得しました。また、資生堂は事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアティブRE100に加盟しています。引き続き、化石資源由来エネルギーから再生可能エネルギーへの移行をより加速させていきます。
- ※掛川工場、大阪茨木工場、福岡久留米工場、上海工場、北京工場、新竹工場(台湾)、イーストウィンザー工場(米国)、ジアン工場(フランス)、バル・ド・ロワール工場(フランス)、グローバルイノベーションセンター(横浜)

フランスのバル・ド・ロワール工場に設置された太陽光パネル
省エネ、エネルギー効率の促進
資生堂が運営する世界各国・各地域の全工場と物流センターでは、毎年CO₂排出量削減の数値目標を設定しており、2025年度は前年比3%のCO₂削減を目標としてエネルギー消費量の削減に取り組んでいます。また、環境マネジメントシステムISO 14001※1に基づき、目標に対する進捗状況を月次で評価し、施策に取り組んでいます。具体的には、工場や物流センターの照明のLED化による消費電力の低減、フォークリフトの電動化などによるCO₂排出量削減のほか、EMS(エネルギーマネジメントシステム)※2を導入し、電気や蒸気、圧縮空気の関連設備ごとのエネルギー消費量やCO₂排出量の情報を可視化し最適化しています。

大阪茨木工場および隣接する西日本物流センター
掛川工場では、中央エネルギー棟から各生産棟への蒸気送気において、EMSデータ分析により熱の損失があることがわかり、各生産棟にヒートポンプを設置することで熱の損失を減らし、エネルギー効率を高めることに成功しました。また、西日本物流センターでは、建物外壁に高断熱パネルを設置して室温調整に役立てています。アメリカ物流センターでは、建物のエネルギー性能の初期評価として、ASHRAE※3レベル1エネルギー監査を完了しました。
社内啓発活動として、資生堂では、国内全社員を対象にサステナビリティのe-ラーニングプログラムを実施し、さまざまな事業活動がCO₂排出につながっていることや、節電や省エネの推進など、環境課題の解決を全員で取り組まなければならないことを伝えています。プログラム修了時にはチェックテストを実施し、社員の理解度の把握にも努めています。また、製造プロセスで多くのエネルギーを必要とする工場では、省エネおよび脱炭素の基礎教育のトレーニングプログラムに加えて、設備管理担当者に対してEMSを活用した省エネに関する勉強会を定期的に実施ししています。EMSデータの分析方法の習得や、参加者同士での分析結果のディスカッション、工場間の情報共有などを通し、省エネ活動に対する専門性の向上に取り組んでいます。
- *1:すべての工場と物流センターにおいてISO 14001の認証取得に向け推進(2023年末までにすべての工場、2024年末までに西日本物流センターおよび台湾物流センターにおいて取得)
- *2:情報通信技術を用いてエネルギーの使用状況を可視化することで、エネルギー負荷平準化などエネルギーの効率的な利用を実現するシステム。国内全工場および海外工場(台湾工場、バル・ド・ロワール工場)で導入済み、その他の各国各地域の工場でも順次導入予定
- *3:アメリカ暖房冷凍空調学会(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)
インターナルカーボンプライシングの導入
資生堂では、自社の活動で使用するエネルギー由来のCO₂排出のうち、約60%が工場での生産活動に由来しています。このため2023年より、工場設備の投資判断にインターナルカーボンプライシング(ICP)を導入しています。社内炭素価格を設定し、2024年から当社の工場における省エネ設備や再生可能エネルギー設備などの脱炭素投資判断への活用を始めました。
自社サイト以外のバリューチェーン(Scope 3)におけるCO₂排出量削減の取り組み
バリューチェーン全体での排出量削減においては、間接的な排出についても把握し、積極的にアプローチしていくことが求められます。
資生堂は、バリューチェーン上の間接排出について、LCA(ライフサイクルアセスメント)の手法に基づき、2011年から算定を行ってきました。その継続的な評価結果をもとに、事業の中でCO₂排出量の大きな活動を特定し、科学的根拠に基づいた長期の削減目標の設定と、ステークホルダーとの協働による削減を進めています。
環境負荷の軽減に対応した原材料の選定・活用
資生堂は、グリーンケミストリーの原則を踏まえ※1、環境負荷の軽減に対応した原材料の選定を進めています。パーム油、紙の調達においてはNDPE(No Deforestation, No Peat, No Exploitation:森林破壊ゼロ・泥炭地開発ゼロ・搾取ゼロ)を支持し、環境だけでなく、人権など社会面も重視した持続可能な原材料の調達を行っています。容器に関しても、リサイクル樹脂の採用を推進するなど、開発に伴うCO₂排出量の削減に努めています。
また、当社はバリューチェーンからの間接的なCO₂排出量のうち40%以上を占めるサプライチェーン上流のCO₂排出量削減を目指し、2022年にCDPが実施する「CDPサプライチェーンプログラム」※2のメンバー企業となりました。2024年は、プログラムの参加対象として戦略サプライヤー26社にCDP質問書への回答を依頼。得られたデータは資生堂のScope 3の算定と削減のために活用しています。
- ※1:人や環境に有害な物質の使用や発生を低減または排除する化学製品およびプロセスの設計のこと
- ※2:メンバー企業がみずからのサプライヤーに対し、気候変動・水・森林に関わる情報開示についてCDPプラットフォームを用いて求める取り組み
輸送時のCO₂排出量削減
資生堂は、出荷における輸送ルートの最適化や積載効率の改善を図るため、例えば日本国内においては他企業との共同配送を行うほか、EVトラックの導入を拡大しています。日本からの海外向け輸出では、パレタイズ※により積載効率を向上させています。
納入頻度の多い容器サプライヤーを中心に、輸送用の包装材の適正化や輸送保護材の再利用などより、廃棄物の削減およびCO₂排出量削減に努めています。可能な限り輸送資材を簡素化することで、店頭での廃棄物削減にも貢献しています。
さらに、容器調達時においては容器サプライヤーと連携し、当社の生産拠点と最も近いサプライヤーの拠点で生産を行う取り組みを推進しています。
- ※倉庫での、パレットへの製品積み付け

資生堂製品配送用EVトラック
廃棄物の削減
資生堂は、サーキュラーエコノミー実現に向けた取り組みの一環として、廃棄物削減に取り組んでいます。国や地域ごとに定められた廃棄物管理に関わる法令や規制を遵守するとともに、バリューチェーン全体を通して資源の使用を最適化し、廃棄物の発生を抑制しています。また、自社で発生する廃棄物については長期にわたり抑制、再利用、再資源化に取り組んできました。2003年には国内工場でゼロエミッション※1を達成し、現在に至るまで廃棄物の分別と資源化の活動を継続しています。
各工場で排出される廃棄物の量と種類に関して、本社と工場で月次の相互確認を行い、廃棄物の削減とリサイクル化の取り組みを進めています。国内工場では、電子マニフェストに基づく廃棄物量管理データを運用し、廃棄物の処理状況を確認することで、データの透明性確保と、法令遵守の徹底に努めています。工場での具体的な廃棄物発生量の抑制策として、排水処理の過程で発生する汚泥を脱水・乾燥し、減容しています。その他にも那須工場では、一部液体原料の納品方法をドラム缶による納品からタンクローリー車に変更することで廃ドラム缶の発生量を削減しました。また、輸送箱の再利用や、廃棄物を素材別に厳密に分別管理して資源化するなど、リユース・リサイクルを推進しています。2023年にはプラスチック包装などの容器包装や製品の輸送時に使用していた段ボールを全面的に見直し、品質を担保しつつ使用する資源を最小化する取り組みを進めています。また、紙資源に加えて、廃プラスチックについても圧縮・溶融により減容化し、リサイクル資源として有価化しています。これらの活動の結果、2022年までに世界全工場で埋め立て廃棄物ゼロ※2という目標を2020年に前倒しで達成し、現在も維持しています。その後も、大阪工場・大阪茨木工場では使用済み食用油をジェット機燃料SAFの原料としてリサイクルするなど、循環型社会に貢献しています。
その他、容器包装の簡素化、能書の廃止、段ボールなど輸送資材の軽量化や削減など、自社サイト以外から発生する廃棄物についても取り組みを進めています。加えて、需要予測精度の向上および生産調達リードタイム短縮により、余剰在庫による製品廃棄の最小化を図っています。
- ※1:廃棄物の再資源化率99.5%以上。法令で埋め立て指定の廃棄物を除く
- ※2:法令で埋め立て指定の廃棄物を除く。2023年も全工場で埋め立て廃棄物ゼロを目標として維持
社員教育
日本国内では、資生堂グループ会社の廃棄物処理実務の担当管理職および担当者に対して、廃棄物処理法の理解と削減活動促進のためのオンライン講習会を開催しています。工場や事務所から排出される廃棄物の処理を処理業者に委託する場合、処理業者のアセスメントを行うこと、廃棄物が適切に処理されていること、産業廃棄物管理票(マニフェスト)管理の徹底、実地確認の重要性を伝えています。受講者は資生堂独自のチェックリストをもとに遵法の徹底に努めています。
役員の長期インセンティブ型報酬における環境関連指標
資生堂では役員報酬において、2019年度より業績連動型株式報酬の一種であるパフォーマンス・シェア・ユニットを導入し、毎年支給することにより中長期的な企業価値の創造を動機づけています。その評価項目として「社会価値指標」を採用し、20%の評価ウェイトを設定しています。「社会価値指標」は複数のESG項目からなり、環境側面では「CO₂排出量削減」を目標に採用しています。
CO₂排出量削減に関する受賞
CDP Aリスト選定〈気候変動・水セキュリティ〉
資生堂は、国際的な非営利団体であるCDPより、「気候変動」および「水セキュリティ」分野の透明性とパフォーマンスにおけるリーダーシップが認められ、2024年度のAリスト企業に選定されました。「気候変動」分野では3年連続、「水セキュリティ」分野では初の選定となりました。
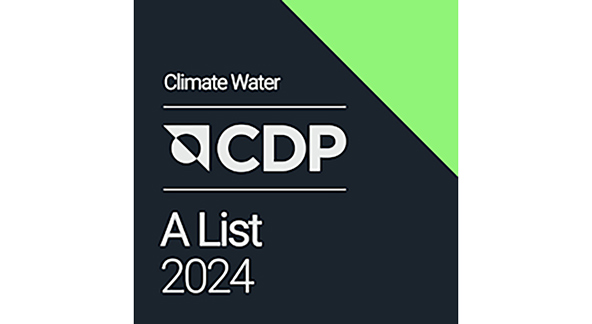
Scope 3のカテゴリーごとの算定方法
| カテゴリー | 説明 | 内部データ | 排出係数 |
|---|---|---|---|
1.購入した製品・サービス |
原材料、包装資材、宣伝広告サービス、パーム由来原料の生産に伴う土地利用転換などサプライチェーン上流からの排出 | 原材料調達量 POSM調達量 メディア宣伝広告費 パーム・紙関連の原材料調達量 |
IDEA v3.1 Ecoinvent 3.9 Reference-1 Reference-2 |
2.資本財 |
資本財を製造する際に発生する排出 | 設備投資額 | Reference-1 |
3.Scope 1・ 2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 |
エネルギー・燃料の採掘、採取、精製、輸送の過程で発生する排出 | エネルギー消費量 | IDEA v3.1 |
4.輸送・配送(上流) |
調達輸送、出荷輸送、廃棄物の回収による排出 | 原材料調達量 製品重量(輸送量) 工場-販売店間の距離 移動手段 |
IDEA v3.1 Ecoinvent 3.9 |
5.事業から出る廃棄物 |
事業活動から排出される廃棄物処理の過程で発生する排出 | 素材別・廃棄処理方法別の廃棄物発生量 | IDEA v3.1 |
6.出張 |
従業員の出張・外出移動に伴う排出 | 移動費 行先別移動回数 移動距離 |
IDEA v3.1 Reference-1 |
7.雇用者の通勤 |
従業員の通勤に伴う排出 | 通勤費 | IDEA v3.1 Reference-1 |
8.リース資産(上流) |
リース物件(倉庫) | 電力・燃料使用量 | IDEA v3.1 |
9.輸送・配送(下流) |
販売や保管による排出 | 販売数量 製品の底面積 |
Reference-4 |
10.販売した製品の加工 |
販売製品は、加工の必要がないため該当なし | |
|
11.販売した製品の使用 |
製品使用時に発生する排出 | 製品使用時のエネルギー、水、消耗品の使用量 | IDEA v3.1 |
12.販売した製品の廃棄 |
内容物成分の分解に伴う排出および製品廃棄物の輸送や廃棄物処理の過程で発生する排出 | 成分および容器素材の分子を構成する化石資源由来炭素の量 素材別の廃棄物発生量 |
IDEA v3.1 |
13.リース資産(下流) |
該当なし | |
|
14.フランチャイズ |
該当なし | |
|
15.投資 |
非連結関連会社および株式投資先からの排出 | 非連結関連会社および株式投資先からのScope 1およびScope 2排出量 株式の保有割合 |
- |
Scope 3排出量の計算方法
1)サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース v3.2
2)Germer, J. et al. (2008) Environment, Development and Sustainability, 10, 697-716
3)地球温暖化対策推進法 算定・報告・公表制度における算定⽅法・排出係数⼀覧
4)2050年カーボンニュートラルに向けたチェーンストア業界のビジョン(基本方針等)
業界全体の環境負荷の定量的把握とCO₂排出量削減に向けたイニシアチブへの参画
資生堂は、化粧品業界をはじめとしたグローバルな各イニシアチブに積極的に参画し、CO₂排出量の計測方法に関するルール策定や環境影響評価手法などの開発を通じて、自社だけでなく国内外の化粧品業界全体の環境負荷の定量的把握とCO₂排出量削減に努めています。
- ●日本化粧品工業会(粧工会)のサステナビリティ指針に賛同し、2000年代後半より同会の取り組みの一環として化粧品業界のCO₂排出量削減に向けた排出量の計測方法に関する標準ルール策定をリード。2025年からは、国内での取り組みとして粧工会における新たなCO₂排出量計測ルールの策定に向けたタスクフォースに参画
- ●2011年には、カーボンフットプリント日本フォーラム(現LCA日本フォーラム)を通じてCO₂排出量の計測とコミュニケーションの重要性に関する政策提言に参画
- ●2018年からは、化粧品容器のCO₂排出量およびその他の環境影響の計測ルールを策定するべくグローバルな化粧品企業数社によって発足したSustainable Packaging Initiative for CosmEtics(SPICE)に日本企業として初めて参画、また2021年からは化粧品の環境影響評価とスコアリングシステムの開発を目指すEcoBeautyScore Consortium(EBS)にも参画
- ●CO₂排出が生物多様性や生態系に与える影響の観点では、影響の定量的評価を目指して2024年にスタートした内閣府および環境省主催の産官学連携の取り組み「ネイチャーフットプリント指標の開発」に参画
関連リンクはこちら
日本化粧品工業会(粧工会)サステナビリティ指針
Sustainable Packaging Initiative for CosmEtics(SPICE)
EcoBeautyScore Consortium(EBS)
水資源の活用と保全
水は、多様な生きものや人々の暮らしに欠かせない自然の恵みであり、流域全体で繰り返し使われる共有資源です。化粧品事業においても、化粧水などに配合される水はもちろんのこと、原材料となる植物の生育、生産現場における温度制御や設備洗浄、製品使用時のすすぎ、廃棄物の処理にいたるまで、さまざまな場面で水を利用しています。
一度私たちが利用した水は、排水処理を経て、きれいな水として再び流域に戻り、その地域で暮らす人々や企業により再び利用されます。広い視野で捉えると、流域ごとに、また同じ流域内においてさえも伏流や湧昇、季節変動といった自然の要因だけでなく、社会による利用の状況によって水資源の状況は異なります。このため、企業においても自社サイトでの水利用の管理とともに、流域や周辺地域まで視野に入れた活動を進めていくことが大切です。
資生堂は、自社サイトにおける製品の生産時に、取水だけでなく排水の量や温度、排水処理後の水質について法令で定められた基準値同等以上の水質になるように浄化設備による処理および水質の定期的なモニタリングを行っています。また、地下水利用のある工場の周辺流域の水環境調査を行い、流域のステークホルダーと協働した水資源管理(Water Stewardship)※の考え方を取り入れた活動を進めています。加えて、原材料素材の生産から使用・廃棄にいたるバリューチェーンの観点で、水に関する環境影響とリスクの把握にも努めています。
- ※自社の操業に関わる水の管理にとどまらず、流域の水資源への責任に対して行動すること
中長期目標と実績はこちら
生産プロセスにおける水資源の活用と消費量削減
直接的な水利用に関しては、資生堂自社サイトにおいて2026年に対2014年比で水消費量40%削減という目標を掲げ、各国各地域の工場の生産プロセスにおける水消費量の削減に取り組んでいます。2023年以降は継続して目標を達成しています。
具体的な取り組みとして、将来の雨量の減少が懸念される欧州に立地するフランスのバル・ド・ロワール工場では、従来の水消費量の削減に加えて洗浄設備のノズル形状を工夫することで1回の洗浄に使用する水の消費量を従来の30%削減しました。また同工場とジアン工場で水消費量をリアルタイムで可視化するシステムを導入し、消費量の抑制や漏水などの異常の早期発見につなげています。設備の効率化やメンテナンスによる着実な削減にも取り組んでおり、大阪茨木工場・那須工場では自動洗浄機や真空ポンプの稼働時間の適正化により水消費量の削減を実現しました。また、工場において水消費量のモニタリングポイント(計測点)を増やすことで、水の消費が多い設備やプロセスの特定を行っています。全生産工場の水消費量は毎月報告されており、目標に対する進捗をトラッキングするとともに、目標達成のための仕組みを構築しています。
例えば、掛川工場では計測点のデータを分析し、水消費量削減箇所の特定や改善策を見いだすトレーニングを各職場の環境担当者へ実施しています。この取り組みにより、社員の節水についての意識が向上し、水消費量の削減につながる有効な施策が立案・実行されています。

那須工場の水処理施設
また、使用した水を浄化し、再利用またはリサイクルする循環型の水利用にも注力しています。
掛川工場では、排水の放流水の一部をリサイクルして原動力設備の補給水に利用する「排水再利用システム」を2023年に導入しました。大阪茨木工場でも、製造釜の冷却水を循環させて再利用しています。また、那須工場では、全水消費量の約半分を占める純水製造設備の稼働の最適化や、逆浸透膜を用いた排水の再利用に取り組んでいます。
2024年以降の新たな試みとして、海外の国と地域では新竹工場や上海工場においても、純水装置からの排水やエアコンの結露を製造設備の冷却水としての利用に加え、雨水を溜めてサイト内の緑化に用いるなどの取り組みを進めています。
その他、フランスのジアン工場ではフレグランス製品の製造設備と輸送のための部品洗浄を水洗浄からアルコール洗浄に変更し、かつ使用したアルコールはリサイクルしています。
水スチュワードシップ(コミュニティにおける水資源の取り組み)
資生堂は、地域と連携した2次利用やサプライヤーとの取り組みなど、流域の共有財産としての水資源管理を進めています。
将来の雨量の減少が懸念される欧州に立地するフランスのバル・ド・ロワール工場では、年に数回、地域の他の業種の方々と好事例や法規制に関する情報共有を行っています。水ストレス※が高い中国の上海工場では地元の環境保護協会に参画し、環境法令を含む環境関連情報(廃水処理、中水リサイクルを含む)などを積極的に取得し、工場の節水活動に活用しています。
また、節水を推進している政府に対して、毎月の水消費量を報告し、水利用率向上と節水管理強化に取り組んでいます。
那須工場は、地下150mの深層帯水層からくみ上げた地下水を利用しています。使い終わった水も貴重な資源として適切に処理し、厳しい自社基準に合格した排水を放流することで、農業用水として2次利用されています。また流域全体の水環境を理解するため、周辺地域の調査を進めています。2024年には、コンピューター上でのシミュレーションだけでなく、周辺田園からの地下浸透について地元高校や農家の協力のもと調査を行いました。
神崎川に隣接する大阪工場では2002年から「大阪アドプト・リバー・小松橋」の協定を大阪府と締結しています。神崎川クリーンキャンペーンでは、近隣の団体・企業・行政と一緒に清掃活動を行っており、2024年には社員とその家族の計47名が参加しました。
さらに、資生堂の自主的な取り組みとして大阪工場と大阪茨木工場の社員からボランティアを募り、神崎川の周囲1.2kmを対象に環境美化活動も実施しています。2024年には年間4回実施し、延べ236人により計56kgの投棄物を回収しました。参加者の環境保全への意識を高めるとともに、地域に親しまれる豊かな河川環境づくりに努めています。
サプライチェーン全体での水消費量削減に向けた取り組みも進めています。例えば、資生堂が戦略サプライヤーの工場を訪問し、設備の洗浄水について、工業用水から品質が確認された周辺の排水処理水へ切り替えるようアドバイスを行いました。これにより、水の循環利用が可能となり、水消費量の削減につなげることができました。

第19回神崎川クリーンキャンペーンの様子
- ※人々や環境の需要を満たすのに十分な量の水がない状態
自社サイトにおける生物多様性保全
2024年、掛川工場の敷地内緑地3.45ヘクタールが「資生堂掛川自然共生サイト」として、環境省が定める「自然共生サイト」に認定されました。「自然共生サイト」は、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」で掲げられた2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする「30by30目標」に基づき、民間の取り組みなどによって生物多様性の保全が図られている区域を広げていくことを目的とした認定制度です。

サイト内は里地里山のような樹林環境を有しており、多様な在来種が生息する豊かな生態系が保たれています。工場敷地内にある事業所内保育所「カンガルーム掛川」の園児が植物採集などで生きものとふれあう場になっていること、企業資料館など近接する施設に美しい景観を提供し、ブランド発信や訪問者の憩いの場になっていることなども評価されました。今後は、緑地管理の継続に加えて、サイト内の生物を対象とした専門調査やモニタリングを実施していきます。
農作物の受粉に重要な役割を担っているミツバチの減少が懸念されている欧州では、フランスのバル・ド・ロワール工場およびジアン工場がミツバチの保護と地域の生態系の保全をサステナビリティ計画に盛り込んでいます。ミツバチの巣箱を設置するとともに、工場敷地内での農薬の使用を禁止しています。設置したミツバチの巣箱からは、2024年は約86kgのハチミツが生産されました。
またアメリカ工場では、工場周辺の1万3,300㎡の敷地で、在来植物を育て生物多様性を守る取り組みを進めています。
2025年からは養蜂会社と契約を締結する予定です。敷地にハチを放つことで植物の受粉を助け、生物多様性の保全に貢献していきます。

カンガルーム掛川

アースデーでの活動
気候/自然関連財務情報開示の取り組み
資生堂は、気候変動問題による事業成長や社会の持続性に与える影響の重大性を踏まえ、気候変動に関してはTCFDおよびISSBの枠組みを、自然・生物多様性に関してはTNFDの枠組みとLEAPアプローチを参照して情報開示を行っています。脱炭素社会への移行、および気候変動に伴う自然環境の変化によって引き起こされる長期的な気候関連のリスク/機会について、1.5 / 2℃シナリオと4℃シナリオ、それぞれの短期・中期・長期の定性的・定量的な分析を試みました。自然に関しては、生物多様性の喪失や水資源の動態を考慮した定量的な長期リスクを特定し、「資生堂 気候/自然関連財務情報開示レポート」として公開しました。
ガバナンス
資生堂では、ブランド・地域事業を通じて全社横断でサステナビリティの推進に取り組んでいます。サステナビリティ関連業務においては、迅速な意思決定と全社的実行を確実に遂行するため、専門的に審議する「Sustainability Committee」を設定し、2023年も定期的に開催しました。資生堂グループ全体のサステナビリティに関する戦略アクションや方針、気候変動と自然環境に関するリスクおよび機会や人権対応アクションなど具体的活動計画に関する意思決定、中長期目標の進捗状況についてモニタリングを行っています。出席者は代表執行役を含む経営戦略・研究開発・サプライネットワーク・広報、およびブランドホルダーなど各領域のエグゼクティブオフィサーで構成され、それぞれの専門領域の視点から活発に議論をしています。その他、特に業務執行における重要案件に関する決裁が必要な場合は「Global Strategy Committee」や取締役会に提案もしくは報告しています。
確実な業務執行・推進を行うため、「Sustainability Committee」の下部に、主要関連部門の責任者から構成される「Sustainability TASKFORCE」を設定し、長期的な目標達成に向けての推進方法やサステナビリティに関連した課題解決について議論し、その他関連部門や地域本社・現地法人を巻き込んだ活動を行っています。
戦略
気候関連リスクおよび機会については1.5 / 2℃から4℃の範囲で気温上昇を想定し、RCP-SSPシナリオに沿って分析を実施しました。移行リスクについては、脱炭素社会への移行に伴う政策、規制、技術、市場、消費者意識の変化による要因を、物理的リスクについては、気温上昇に伴う洪水の発生や気象条件など急性/慢性的な変化要因について、各シナリオ条件における影響を分析しました。
2030年時点における移行リスクとして、炭素税によって約0.5~8.7億円規模の財務影響が発生する可能性を予測しています。物理的リスクについては、洪水により約9億円、水不足により約32億円の潜在的なリスクを見込んでいます。機会に関しては、1.5 / 2℃シナリオにおいて、消費者の環境意識の高まりに伴い、サステナビリティに対応したブランドや製品への支持が強まると予想されます。4℃シナリオにおいては、気温上昇に対応した製品の販売機会が拡大すると予想されます。イノベーションによる新たなソリューションの開発により、サステナブルな製品を提供していくことで、リスクの緩和と新たな機会の創出を目指しています。
リスクと機会のシナリオ分析
| |
リスク | 機会 | |
|---|---|---|---|
| 移行リスク (主に1.5/2℃) |
|
|
|
| 物理的リスク (主に4℃) |
急性 |
|
|
| 慢性 |
|
||
- ●がついている要因は定量分析も実施しています
自然関連リスク/機会に関しては、ライフサイクルアセスメントによってバリューチェーンを通じた生物多様性への影響側面の定量分析を行い、特に原材料調達における影響が大きいことを明らかにしました。そこで、TNFDが推奨するLEAPアプローチに沿って、生物多様性への依存度の高い化粧品原材料について原産地を推定し、土地転換による潜在的な影響の評価と、依存側面における物理リスク分析としてミツバチなどの花粉媒介者による生態系サービスの金額化を行いました。同時に、移行リスクとして、サステナビリティ関連規制に関わるリスク分析を、気候変動問題とあわせて実施しています。
リスクマネジメント
資生堂は、中長期の事業戦略の実現に影響を及ぼす可能性のあるリスクを総合的・多面的な手法を用いて抽出し、特定しています。そのなかには、「環境対応(気候変動・生物多様性など)」「自然災害・感染症・テロ」といったサステナビリティ領域のリスクも含まれています。気候変動や生物多様性に関連するリスクも、事業継続や戦略に影響を及ぼす要因の1 つとして科学的または社会経済的なデータに基づいて分析され、気候変動や自然災害に関わるリスクとして全社のリスクマネジメントに統合されます。特定されたリスクは、重要度に応じて「Global Risk Management & Compliance Committee」や「Global Strategy Committee」にて対応策などが審議されています。また、必要に応じて取締役会に提案もしくは報告される体制となっています。
指標と目標
資生堂は、CO₂排出量削減を目標として設定し、また定期的に気候変動に伴う状況をモニタリングし、対応策を講じることで、リスクの緩和に貢献しています。特にScope 1およびScope 2のCO₂排出量については2026年までにカーボンニュートラル※1を達成することを目標として設定しました。また、バリューチェーン全体におけるCO₂排出量削減目標に関しては、1.5℃経路に整合した2030年目標に対して、SBTイニシアティブ(SBTi)※2の認証を取得し、CO₂排出量削減に取り組んでいます。
生物多様性に関しては、環境への影響の大きな紙やパーム由来原料について、認証原材料への切り替えを進めています。
Scope 1・2のCO₂排出量削減のため、インターナルカーボンプライシング(ICP)制度の導入を決定し、2024年から省エネ設備や再生可能エネルギー設備などの脱炭素投資判断への活用を始めました。※3
- ※1:Scope 1およびScope 2の排出量が対象。クレジットなどを活用したオフセット含む
- ※2:パリ協定目標達成に向け、企業に対して科学的根拠に基づいた温室効果ガスの排出量削減目標を設定することを推進している国際的なイニシアティブ
- ※3:2024年現在のICP価格:130米ドル/t-CO₂
企業情報
-
Who we are
-
History
-
プロフィール
-
ガバナンス
-
品質保証
-
資生堂の生産・供給
-
地域/事業
ブランド
-
プレステージ
-
プレミアム
-
インナービューティー
-
クオリティーオブライフ
サステナビリティ
-
戦略・マネジメント
-
社会
-
環境
-
コーポレートガバナンス
-
レポート・データ
-
関連情報
イノベーション
-
資生堂の研究開発について
-
研究領域
-
研究成果
-
公的研究費
投資家情報
-
IRライブラリ
-
個人株主・投資家のみなさまへ